前回の投稿はコチラ↓
2020.09.04 今回は、「田舎暮らしに必要なモノ ~ 草刈り作業編」と称し、これがなくては田舎暮らしはできないと言っても過言ではないレベルの必須作業「草刈り」で必要なモノを紹介します。どれぐらい必須作業かと言われると、移住前の地域面談で「草刈り経験は?」と聞かれるレベルです。…
僕は2019年春に豊田市の中山間地域、いわゆる田舎に移住しました。定住人口 ”となったわけですが、田舎との関わり方は“定住”だけではありません。関係人口 ”という田舎との関わり方と、僕が関わる田舎について書いてみました。
田舎との関わり方
田舎との関わり方は、大きく分けると3つに分類されます。
田舎に観光に来るのが“交流人口 ”、田舎に移住するのが“定住人口 ”、そして、“交流人口”でもなく“定住人口”でもない、地域や地域の人々と多様な関わり方をする“関係人口 ”の3つです。
この“関係人口 ”という概念が今、地域づくりの新しい担い手として期待されています。関係人口』ポータルサイト ”というサイトを用意しその創出に躍起になっているぐらい、つまりもう国策レベルで期待されています。
関係人口
田舎は、都市部への人口の流出や少子高齢化の進行から、児童生徒数の減少による学校の統廃合、空き家や耕作放棄地の増加、地域のお祭りや道路等の草刈りといった集落機能の維持が困難な状況になりつつあるなど、様々な課題を抱えています。
これらの課題を解決するもっともベストな方法は、定住人口を増やすことです。
定住人口が増加し、地域に子どもが増えれば、児童生徒数が増えるので学校の統廃合が回避できます。
「小学校が廃校になると、その地域からは人が減る。だから小学校の廃校は何としてでも回避しなければならない。 」
僕が関係人口として関わる地域の方が仰っていた、とても印象的な言葉です。
我が家が暮らす地域は、豊田市内の中山間地域でもっとも定住促進活動が活発であり、その結果が出ている地域です。近年児童生徒数が右肩上がり で増えています。
空き家に定住者が入り、その定住者が耕作放棄地を復活させ、人手が増えることによってお祭りもできるし草刈りの負担も分散される……我が家がある集落が正にそれです。
我が家がある集落は、集落世帯の1/3がIターン世帯、つまり移住者世帯です。
我が家も、10年超耕作放棄されていた田を、今年復活させようとしています。このように、中山間地域が抱える課題は、定住人口を増やすことで解決することができます。
が、そんな簡単に定住人口が増えるのなら、誰も困らない わけです。
様々な事情でその地域に“定住”することはできない。
このような意識で、その地域と関わる人が“関係人口”です。
僕が“関係人口”として関わる田舎は、我が家が今の家に定住するまでに出会った田舎です。この地域と出会うことがなければ、僕は今の家に定住はしていない でしょう。
僕が関わる田舎 ~ 関係人口の具体例 豊田市稲武地区 ~ INABU BASE PROJECT
僕にとってINABU BASE PROJECT 田舎と関わるきっかけ となった、とても大きな存在です。
豊田市稲武地区 は豊田市の北東に位置し、長野県・岐阜県との県境があります。2,200人 、高齢化率(65歳以上の人口割合)は51% 、高齢化率50%越えで限界集落になりますので、地区平均で見ても限界集落 です。
INABU BASE PROJECTは、“愛知のチベット「稲武」 そこで始まる働き方革命 ”を旗印に、稲武に本社がある自動車用シートカバーメーカー“トヨタケ工業”が中心となって設立された地域の新規定住者受け入れを支援する団体“OEPN INABU実行委員会”が展開しているプロジェクトです。
このプロジェクトは、従業員約100人を抱えるトヨタケ工業が、10年後にはその半数が60歳以上になってしまうことから、従業員の若返りを図るために新卒採用を10年ぶりに再開することがきっかけで始まりました。
前述の通り、稲武は高齢化率が50%を超えているため、地元での新卒採用は難しい状況にあります。働きやすさや中山間部の魅力をPRすることで、地区外から若い人材を呼び込もう としているわけです。
INABU BASE PROJECTですすめる働き方改革は、具体的には、平日週3日は事業所で働き、土日は稲武でトレッキング、マウンテンバイク等の山岳ツアーガイド業をするなどして、残りの平日を休むといったものです。
僕は2017年秋から、“トレッキング、マウンテンバイク等の山岳ツアーガイド業 ”を行うためのトレイル(コース)の開拓メンバー として、このINABU BASE PROJECTに加わりました。
僕はトレイルの開拓メンバーとして加わっただけで、トヨタケ工業に入社しなければこのプロジェクトに携われないわけではないのです。INABU BASE PROJECTを介して、稲武の関係人口となった わけです。
当時の僕は、自分の趣味であるマウンテンバイクで胸を張って走れるコースが少ないことを感じていました。
それから今日に至るまで、INABU BASE PROJECTでは様々な経験をさせてもらいました。志を同じくする仲間たち がいなければ、今の僕はないと言っても過言ではありません。
僕のINABU BASE PROJECTにおける活動のモチベーションは、“自分たちが走る道を自分たちで作る”というのが最初の動機ではありますが、徐々に“自分たちがやっていることは、定住人口増加に繋げるための種まき ”に変わっていきました。
その活動の成果は、早々に見えることになります。
INABU BASE PROJECTがきっかけとなり、トヨタケ工業は2020年度までに中途3人、新卒2人を採用することに成功 しました。5人全員が、まずは関係人口として稲武に関わり始め、トヨタケ工業への入社をきっかけに稲武の定住人口となった わけです。そんな5人のうちの1人、2019年度に新卒としてトヨタケ工業に入社した遠藤颯くん のインタビューが、“とよたでつながるローカルメディア縁側 ”に掲載されています。
2020.03.23 愛知県豊田市の北東部に位置し、岐阜県と長野県との県境にある稲武地区。森林が面積の9割を占 める山あいの町で、中心部の標高は約500m。人口は約2,230人(2019年)うち、約半数が65歳 以上だ。
…
関係人口主体で始まったINABU BASE PROJECTは、プロジェクトをきっかけに定住人口が増加したことで、現在は稲武に定住したメンバーを中心とした言わば第2ステージとなる活動 がなされています。
稲武には、我が家が愛する家具と暮らし+カフェヒトトキ〜人と木〜 もあります。
そんなヒトトキが、山を楽しむ様々なコンテンツと、まちやどとしての機能を持たせた宿泊サービス「hi-bi」 を始めるそうです。
築100年を超える古民家をリノベーションして行うこのサービス、安全祈願祭を終えて着工しているとのことで、稲武のこれからがかなり面白い ことになりそうです。
豊田市栃本町 ~ おいでんトレイル足助栃本
豊田市栃本町 は、足助地区にある13世帯 の集落です。地区 ”であるのに対し、栃本町への関わり方は“集落 ”です。自分の親戚 ”ぐらいの親近感を抱いています。
この栃本町で、関係人口による地域活性化 を目指し、“MTBを人と地域を繋ぐハブに ”をキャッチコピーに活動しているのが、僕が代表を務める“おいでんトレイル足助栃本
INABU BASE PROJECTに参加したことで、自分の手でトレイルを作ることに目覚めた 僕が、同じくINABU BASE PROJECTに参加していた友人 に声をかけ、2018年冬にスタートしたプロジェクトです。
僕と栃本町の出会いは2017年秋。ふれあいフェスタ冷田 ”においでん・さんそんセンター 主催のとよたいなか暮らし博覧会 を介して参加したことでした。とよたいなか暮らし博覧会 だったので、僕の現在にとてつもなく大きな影響をもたらしたイベントです。
2018年3月に、栃本町自治会から桜の植樹イベント“桜の森づくり ”のお知らせをもらい、そこに家族で参加させてもらいました。
この“桜の森づくり”自体も関係人口を創出するためのイベント で、桜を植樹するだけでなく、年に2回の下草刈りなどを通して、継続的に地域と関わり、桜の成長とともに地域との関係も育まれていく という、関係人口創出のお手本のようなイベント です。栃本町自体が関係人口創出に積極的な集落 なのです。
桜の植樹より4ヶ月経った2018年7月、桜を植樹した一帯の下草刈りイベントがありました。
その際に、栃本町自治会より「何か栃本でやりたいことはないか」と聞かれ、「もしMTBで走ってよい山道があったら走らせていただきたい」とお願いしたところ「走れる道がある」ということで、里山を案内していただける運びになりました。
その後、ルート探索等を行い、2018年12月に、“おいでんトレイル足助栃本”が発足し、現在に至るという流れです。
おいでんトレイル足助栃本では、栃本町地内の里山にMTBで走行できるコースを整備させてもらう 代わりに、栃本町で行われる環境美化活動(県道沿いの草刈り)などのお手伝いやお祭りへの参加 をさせてもらっています。
また、整備させてもらったコースの走行会を開催 することで、栃本町への来訪者を増やし、栃本町のファンを増やす = 栃本町の関係人口を創出するお手伝い もさせてもらっています。
今年は、春先に原木しいたけ栽培も、栃本町で有志のご指導の下で行わせてもらいました。
発足から1年半ほどが経ち、発足当初よりも仲間も増え、栃本町の関係人口創出に僅かながらも寄与できていることが誇りであると同時に、今後も引き続き栃本町の関係人口創出に尽力していきたいと思っています。
定住に至らなかった理由
ここまで愛する稲武地区と栃本町に僕が定住しなかった理由は、どちらも条件に合う空き家がなかった からです。
空き家は一期一会、先輩定住者から「ビビビっと来る物件が出たら移住どき 」という話は聞いていましたが、本当にそういう物件ってあるんです。その物件が、我が家の場合は今の家だったということです。
定住に与えた影響
僕は定住前から稲武地区と栃本町の関係人口だったわけですが、僕が定住した旭地区では関係人口と言える関わり方をしたことはありません でした。
では、なぜ僕が稲武地区と栃本町の関係人口だったことが、旭地区への定住に影響をもたらしたかと言うと、僕がそこでの関わりで出会った地域の人がとても素敵だった からです。
地域と関わる前、僕は田舎に対して“閉鎖的なのではないか ”という偏見の目 を持っていました。稲武地区と栃本町に関わることで、その偏見が誤りであったことに気づかされました 。
また、我が家は元々妻の方が移住に積極的 で、僕は街暮らしでもいいじゃんというスタンスでした。田舎暮らしもいいじゃん 」と意識が変わりました。
定住しないという選択肢
田舎との関わり方において、その地域にとってベストなのは定住かもしれませんが、関係人口として関わり続けるというのもベターな選択肢 です。
もっとも、気になる地域がある = 既にその地域と何らかの関わりがある = その地域の関係人口ですから、あなたは既にその地域の関係人口となっている可能性もあります。
大切なのは、地域に自分の想いを押し付けすぎないこと です。地域のことを想い、適切な距離感で、地域が求める力を提供すること が、関係人口としての上手な関わり方 だと思います。



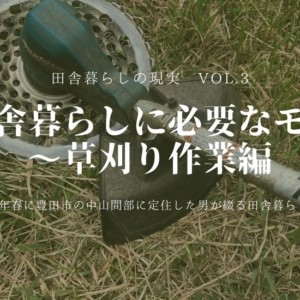







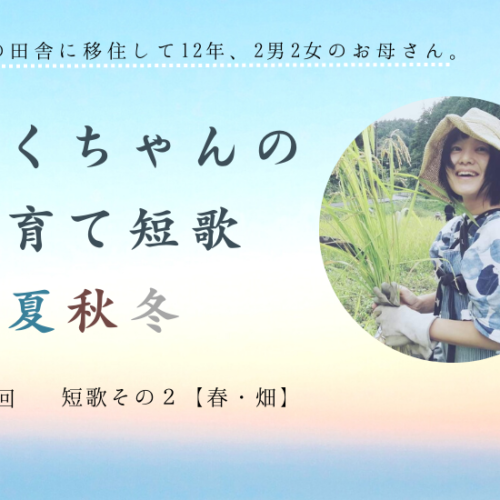




この記事へのコメントはありません。