森のなかで過ごす春夏秋冬【森のちいさなようちえんで育つ おおきな家族第4回】

第4回目は、森のようちえんで過ごす私たちの四季折々のエピソードをお伝えします。
年間通して森の中で過ごしている森のようちえん、ここにいるからこそ見られる場面がたくさんあり、森だからこそ感じられることがたくさんあります。
3~5歳児の幼稚園児は、大人が教え導かなければならないと思っていますか? 森のたまごに関わる大人は、子どもたちから学ぶことが多々あります。それは、私たち大人が自然の中にいることにより、ゆったりとした気持ちで子どもたちを見られるからかもしれません。自然の神秘は、心を大きく動かしてくれます。
そんな中で過ごす私たちのエピソードを森のたまご年長母(まーさん)に伝えてもらいます。
私は東京のベッドタウンと呼ばれる街で幼少期を過ごしました。両親が共働きだったので、都内の保育園へ通っていました。幹線道路沿いの保育園には小さな園庭があり、裸足で駆け回っていました。時々広い公園にも散歩へ出掛け、草花で遊んだ記憶もありますが、野山で遊んだ経験はほとんどありませんでした。
森のたまごに入園したばかりの頃は、保育に入る度に、子ども達と一緒に何をして遊んだらいいのだろう。蛇に咬まれたり蜂に刺されたら処置はどうしよう。木登りしている子どもが落ちそうになったらどうやって助けよう。など、森での経験がないことに不安を感じ、そんなことばかり考えていました。
入園した春、よもぎ団子を作った日のことです。よもぎ団子を作ったことのない私は、前日によもぎと間違えそうな毒を持つ葉っぱの予習をし、保育に備えていました。
子ども達と一緒によもぎを摘み始めると、年長さんが「これがよもぎ。裏が白くて毛があるよ。」と、入園したばかりの子どもや私に教えてくれました。毎年春になるとよもぎ団子を作って食べている子供たちにとって、よもぎはいつもの場所で見慣れている植物であり、間違えようもないものでした。
今でこそ、何かおいしく食べられるものはないかと探しながら保育当番をするようにもなりましたが、当時森のたまご初心者の私にとっては、子どもたちの知識に驚き、尊敬の気持ちを抱いた出来事でした。
他にも、触るとかぶれる草木のこと、蛇や蜂に出会った時にはどうするかということ、木登りする時に安全な枝を選択する見方など、森で活動する時に必要な危機管理に対する知識なども、年上の子どもから小さな子どもへ伝え、またその子どもが自分の経験を重ねて次の子どもに伝える。縦割り保育の中で自然とそんなサイクルができていて、教科書的な大人の説明よりもずっと具体的で理解しやすいように感じています。

そして2年前に現在の拠点へ活動場所を移してから、子どもたちは自分たちだけの場所で、更にのびのびと自由に遊ぶようになっています。毎日同じ場所で同じ仲間と遊んだり、喧嘩をしたり、時には1人で過ごしたり、好きな時に好きなことを好きなだけしています。
森のたまごのお山には、おもちゃはもちろんありません。遊具もありません。ロープや工具などの道具が少しあるだけです。季節によってたくさんの変化を見せる自然の中で、飽きることなく遊び尽くしています。
春
春のお山はやわらかな日差しに包まれ、芽吹きの木々や草花は生命力にあふれ、そこで活動する私たちも元気になります。進級した子どもたちにとっては、卒園した子どもたちがしていた遊びを真似て挑戦する時期でもあります。
木登りやターザンロープ、崖を登ったり滑り降りたりする遊びは、一定の場所で長く定着することはあまりなく、景色を変え、難易度を変えています。それは大人が変えるのではなく、子どもたちがひとつの目的を達成し、次の目標を自ら設定するのです。大人のすることは、子どもに指定された場所が安全かどうかを確認し、命綱になるロープを結んだり、落下した時に大怪我につながるようなものがあれば除去するくらいです。
2年前にお山で遊び始めた頃、子どもたちが夢中になった崖。今では園児の姿を見ることはほとんどなく、小さな親子組の子どもたちが上り下りを楽しんでいます。さらに小さな子どもたちまで見様見真似で進歩していく様子が、こんなに早い段階で見られることに驚かされています。
夏
夏のお山は暑いですが、木々のおかげで日陰も多く、時折吹く風が心地よい季節です。梅雨の雨も子どもたちにとっては遊び道具のひとつになっています。また、人の手がほとんど入らないお山には、多様な生き物たちが生活しています。春夏の子どもたちは、カナヘビやトカゲ、カエルやクワガタを捕まえるのに忙しい毎日です。
昨年から「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金」を受け、とよた森林学校の北岡先生をお迎えして定期的に自然観察会を行っているため、森の生き物への興味が深まっているようです。
小さな生き物たちを捕獲し、飼育する子どももいます。初めてできた相棒をかわいがりすぎたり(子どもの温かい手で触りすぎて)、反対に忘れてしまったりして、時には死なせてしまうこともあります。
先入観のある大人にとっては口出しをしてしまいたくなる場面でもあるのですが(私はしてしまいました)、生きていること、死ぬということを、その子ども自身の心で感じる経験は、今後の子どもたちの成長に必要なことだと捉えています。

秋
実りの秋のお山は、木々は色とりどりの葉や木の実であふれ、空気は日毎にひんやりとしてきます。紅葉でできた赤や黄色のグラデーションのアーチが、冬のおとずれと同時に華やかな絨毯へと変わります。
いつも元気いっぱい外遊びをしている子どもたち、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、おままごともよくしています。
葉っぱや木の実はお花やご馳走になり、斜めに切れている切り株はレジスターになり、冷たい朝に見つけたキラキラの氷は宝石になります。豊かな自然が生み出す色は、子どもたちの想像力をかき立て、色とりどりなファンタジーの世界を広げます。
そこにはテーマや道具は何もいらない、ただただ自由な空間があるだけです。

冬
冬のお山は冷たい風が吹き、心も体も冷えてしまいがちですが、蛇や蜂などの危険生物との遭遇の機会が減り、比較的過ごしやすい季節です。
暖を取るための焚き火は子どもたちが点火しています。火を大きくしたり、維持をするために何が必要か、ここでも年長さんの経験が活かされています。
昼食のお味噌汁や焼き芋、お誕生会の五平餅も焚き火で焼きました。
小さな子どもたちは、年長さんの姿を目に焼き付けて、ひとつ大きくなる準備をする時期でもあります。

自然の中で自由に育つ子どもたちの、生きる力と感性に、私たち大人は日々刺激を受けています。
森のたまご立ち上げ時に、代表遊佐が想いを込めて書いた文章があります。
『小さな草にも、大きな木にも、一つ一つに役割があり、
私たちの生活に欠かせないものを小さな手で触れ、
いろんな気持ちをいっぱい感じ、育ってほしい。
子ども同士の関わり、時間を大切にし、
満足感や、達成感をたくさん味わってほしい。
大人たちは少し口を閉じ、
子どもたちが何をどう選ぶのかそっと見守り、
必要な時には知恵のエッセンス。
大人も子どもも育ち合い、自分らしく生きる・・・』
森のたまごで、自然の中で3年間を過ごすということは、
まさにこのことだと、実感しています。
- コラム
- 松平地区, 森のちいさなようちえんで育つおおきなかぞく
- コメント: 0
関連記事一覧

変わらずに、変わり続ける古民家【「喫茶室転々」マスターが語る...

ポンコツ夫の無計画脱サラ移住日記|第6話 『ぽんぽこ畑』とし...

たくさん迷ったから、たくさん学べたんだ|なぁなぁ!田舎ってこ...

新居は10LDK!古民家リノベのビフォアアフター【いいかげん...

シフォンケーキをこじらせて【「喫茶室転々」マスターが語る暮ら...

懐かしくて新しい豊かな暮らし【はだしで野生をとりもどせ!#3...

激励のメールにうれしさ込み上げる【いなかとまちの交換日記wi...
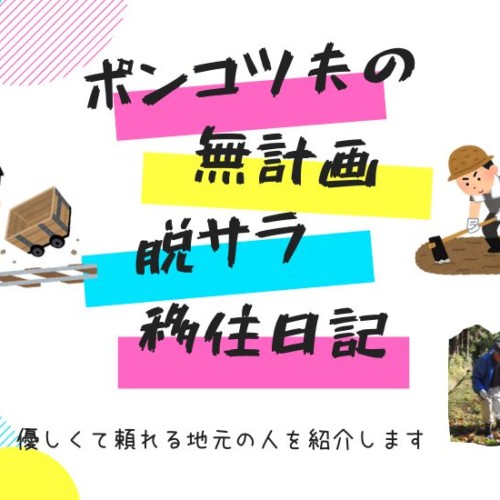





この記事へのコメントはありません。